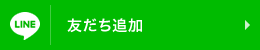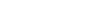薬物治療の個別最適化
HOME > 薬物治療の個別最適化
薬物治療の個別最適化
[入院患者]暴力等が見られるレスパイト入院患者の薬物療法を多職種協働で個別最適化した症例-長野県立信州医療センター

本シリーズでは、薬物治療の個別最適化を行った事例を紹介していきます。
[入院患者]暴力等が見られるレスパイト入院患者の薬物療法を多職種協働で個別最適化した症例-長野県立信州医療センター
今回の症例
既往に認知症、慢性心不全がある80歳代・男性の患者さん。在宅療養されていましたが、夏になると慢性心不全が悪化し度々入院管理となっていました。また、ショートステイの利用を検討したものの、暴力等の問題行動があり、希望するサービスを利用できませんでした。
今回、家族の介護疲れによりレスパイト入院となりました。入院初日から看護師への暴力等があり対応しきれない行動が続いていました。
入院時処方)
| Rp 1 | アンブロキソール塩酸塩徐放性口腔内崩壊錠45 mg | 1回1錠(1日1錠) |
|---|---|---|
| フェブキソスタット錠20 mg | 1回1錠(1日1錠) | |
| フロセミド錠20 mg | 1回1.5錠(1日1.5錠) | |
| 1日1回 朝食後 | ||
| Rp 2 | ラメルテオン錠8 mg | 1回1錠(1日1錠) |
| 1日1回 寝る前 |
薬剤師が解決したプロブレム
#1 認知症による攻撃性に対する治療薬の選択
#2 新規薬剤の効果・副作用モニタリングによる用量調整
入院初日より、ケアの拒否と暴力行為等の問題行動により入院継続困難な状態でした。そのため、医師、薬剤師、病棟看護師、認知症専門看護師、理学療法士、介護福祉士、管理栄養士、医療専門の社会福祉士が集まり多職種カンファレンスを実施し、入院中のケアや治療など、今後の方針について検討しました。
病棟看護師、理学療法士、介護福祉士からの情報では、難聴があること、無理やり動作を制御すると暴力行為が出てしまうこと、几帳面な性格であることなどがわかりました。認知症専門看護師からは、難聴が強く指示が聞こえていないため、ケアに際しては、これから何をするかジェスチャーを交え説明してから開始するようにとアドバイスがありました。
薬剤師は認知症の中核症状に対する認知症治療薬、及び、認知症の周辺症状に対する薬物療法の提案を考えました。多職種カンファレンスで、攻撃性があることから認知症治療薬はメマンチン塩酸塩を、周辺症状に対しては抗精神病薬1)(認知症の周辺症状の興奮や攻撃を落ち着かせる目的として他の薬剤と比較し半減期の短いクエチアピンフマル酸塩25 mgの1日3回定時服用、夜間不眠時の対応としてリスペリドン0.5 mg頓用)の使用を主治医に提案し了承されました。
新規薬剤の導入に際しては、患者さんのリスクとベネフィットを考慮し、主治医から十分説明し家族のインフォームドコンセントを得て、薬物治療を開始しました。
新規薬剤開始にあたり、薬剤師から、これらの薬により眠気、ふらつき、過鎮静、歩行障害、嚥下障害といった副作用が発生する可能性があることを他職種(病棟看護師、理学療法士、介護福祉士)へ提供し、多職種協働で副作用の早期発見に努めました。
薬物療法開始後、他職種(病棟看護師、理学療法士、介護福祉士)と使用薬剤の副作用に関する情報共有をしながら投与量を調整することができました。その後、暴力行為や徘徊についてもコントロールできるほど経過は良好になりました。また、薬物療法と並行して認知症専門看護師の介入もあり、非薬物療法として本人の意思を尊重しながらのケアを実施しました。退院時には、薬物療法と非薬物療法の併用により暴力行為や徘徊を軽減することができ、ケアについての詳細を院内の地域担当者へ情報提供しました。
退院の際、薬剤師からご家族へ退院時薬剤管理指導を実施しました。ご家族には、抗精神病薬の副作用は、使用開始後の早期に出現する場合が多いけれど、1ヶ月以上もしくはさらに長期に使用している段階で出現する可能性もあるため、眠気、ふらつき、過鎮静、歩行障害、嚥下障害等の症状に注意して観察いただくよう説明をしました。ご家族から「連日徘徊のため夜間眠れずにいた、かかりつけ医にも薬物療法の相談ができずにいた」と話があったことが非常に印象的でした。
また、現在、当院では、薬物治療を地域へつなげることが重要と考え、保険薬局への情報提供(薬剤管理サマリー)を積極的に行っています。本症例でも、今後、認知症専門医療機関への受診予定があることから、ご家族の了承を得て、かかりつけ薬局へ薬剤管理サマリーの提供を行いました。その中で、新規薬剤導入にあたり入院中5 mgで開始していたメマンチン塩酸塩については、今後、腎機能を再評価し増量を検討提案いただくよう依頼をしました。
退院後しばらくして、かかりつけ薬局の薬剤師から「患者来局時に易怒性が強くなっていることを感じていた。今後、かかりつけ医、家族と連携を図りながら薬物療法を提案していく」と連絡をいただきました。
今回、地域包括ケア病棟へのレスパイト入院に対して多職種で情報共有し薬物療法の調整を経て、非薬物療法との組合せによって認知症の症状が改善されました。在宅での問題に対して多職種からの多面的な提案が効果的なケアにつながり、本人の日常生活の維持や家族の介護負担の軽減に寄与できました。
退院時処方 ※青字は薬剤師の処方提案による変更箇所
| Rp 1 | フェブキソスタット錠20 mg | 1回1錠(1日1錠) |
|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5 mg | 1回1錠(1日1錠) | |
| フロセミド錠20 mg | 1回1.5錠(1日1.5錠) | |
| 1日1回 朝食後 | ||
| Rp 2 | ラメルテオン錠8 mg | 1回1錠(1日1錠) |
| 1日1回 寝る前 | ||
| Rp 3 | クエチアピンフマル酸塩錠25 mg | 1回0.5錠(1日1.5錠) |
| 1日3回 毎食後 | ||
| Rp 4 | リスペリドン口腔内崩壊錠0.5 mg | 1回1錠 |
| 不眠時 |
今回の薬歴
#1 認知症による攻撃性に対する治療薬の選択
- S 「……」(声かけに目線を合わせるが返答なし)
- O 難聴あり。攻撃性あり。病棟の廊下を往復し、落ち着かない行動がある。
Ccr 27.97 mL/min。糖尿病なし。MRIよりレビー小体型認知症は否定。 - A 認知症治療薬の導入が必要。
認知症の中核症状には攻撃性あるためメマンチン塩酸塩を選択。
認知症の周辺症状には半減期の短いクエチアピンフマル酸塩の定時服用とリスペリドンの頓用を選択。
高齢、腎機能を考慮しメマンチン塩酸塩は5 mg/回から、クエチアピンフマル酸塩は25 mg/回から開始、夜間不眠時のリスペリドンは0.5 mgを1錠。以上を主治医へ提案する。 - P 医師に処方提案、了承されたため、他職種へ新規薬剤の副作用の情報を提供し、副作用の早期発見に努める。
新規薬剤の副作用:眠気、ふらつき、過鎮静、歩行障害、嚥下障害等。
#2 新規薬剤の効果・副作用モニタリングによる用量調整
- S 「……」(声かけに目線を合わせるが返答なし)
- O 薬物療法導入3日目。
拒薬なし。廊下の椅子で寝ていることが多い。
看護師、介護福祉士より、やや傾眠が見られる印象と情報あり。
食事は全量摂取できている。ムセは見られていない。 - A 薬物療法と非薬物療法の併用により入院中の暴力や徘徊は軽減している。
非薬物療法においては、本人の意思を尊重しながらのケア介助を実施できている。
傾眠が見られているためクエチアピンフマル酸塩25 mg/回の投与量の減量を主治医へ提案する。 - P 医師に処方提案、了承され、クエチアピンフマル酸塩錠25 mgは1回0.5錠へ減量。
引き続き、眠気、ふらつき、過鎮静、歩行障害、嚥下障害等の副作用発生状況を確認していく。
実務実習生の疑問に答える
Q1 レスパイト入院とはどのような入院ですか?
「レスパイト」には、休息、息抜きの意味があります。レスパイト入院は、地域で在宅介護・医療を受けている患者の介護者が、何らかの事情により休養が必要となった場合のための入院で、在宅療養を支えるための入院といえます。
Q2 地域包括ケア病棟とはどのような病棟ですか?
地域包括ケア病棟は平成26年度診療報酬改定で新設された病棟で、①急性期治療を経過した患者の受け入れ、②在宅で療養を行っている患者等の受け入れ、③患者の在宅復帰支援等を行う機能がある病棟です。
他の在宅復帰を目指す病棟;回復期リハビリテーション病棟(脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者へのリハビリテーションを提供)や令和6年度新設の地域包括医療病棟(高齢者の救急患者等へのリハビリテーション、栄養管理等を包括的に提供)とは異なり、地域包括ケア病棟は対象疾患に縛りがありません2)。そのため、さまざまな状態の患者さんが入院でき、レスパイト入院も可能になっています。
現在、地域包括ケア病棟における算定要件には病棟薬剤師の配置は求められていませんが、在宅から入院、入院から在宅へと移行する中で、薬物療法における薬剤師の介入は非常に重要であり、多職種協働で薬物療法に取り組んでいます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140619.pdf
https://chiiki-hp.jp/about-hcc
地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立信州医療センター(長野県須坂市)・薬剤部。
薬剤部のスローガンは、「汗をかけ、べそをかけ、恥をかけ、夢を描け!」。薬剤師の臨床能力を向上させるために、フィジカルアセスメントの実践やバイタルチェックによる患者評価、画像読影スキルに力を入れ、患者さん中心の医療を実践している。
各薬剤師は、専門的な視点をもってチーム医療に参加し、地域連携にも力を注ぐなど、多職種と連携し患者さん一人ひとりに寄り添う質の高い医療を提供している。また、当院の連携機関、長野県立病院機構(こども病院、こころの医療センター駒ヶ根、阿南病院、木曽病院)においても、専門分野をはじめ地域医療に積極的に取り組んでいる。
薬剤部紹介はこちら
https://shinshumedicalcenter.jp/department/drug/
「薬物治療の個別最適化」の学修に役立つ新たなコンテンツを検討しています。
本症例への感想など、ぜひご意見をお聞かせください。
薬物治療の個別最適化

-
[外来患者]味を考慮した吸入剤変更提案により、高齢者の過量服薬を回避した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]暴力等が見られるレスパイト入院患者の薬物療法を多職種協働で個別最適化した症例-長野県立信州医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]入院時における初回面談と多職種連携により、ポリファーマシーや銅欠乏の疑いを解決した症例-新潟市民病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]向精神薬多剤併用処方に介入して、過鎮静やイライラを改善した症例-JA尾道総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]乳がん患者のレジメン選択支援を行い、治療が決定、身体的苦痛を解消した症例-獨協医科大学埼玉医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]高齢者の降圧薬併用による生命予後低下と副作用発現の可能性から減薬を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]認知症患者の周辺症状の増強から副作用を疑った症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]人生の最終段階にあるがん患者への疼痛コントロールでACPを実践した症例-西岡病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬剤師間連携により、潜在性甲状腺機能低下症の疑いや口腔内副作用を解決した症例-長崎病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]糖尿病患者の体調の変化から、服薬調整を指導した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]画像で心肥大等を確認し、利尿剤投与に伴う低カリウム血症を解決した症例-川口工業総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]外科的治療と歩行訓練や臥床時の圧迫やずれにより難治化した踵部褥瘡を改善した症例-小林記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]目の縁のただれから、化学療法の副作用を発見した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬物相互作用のチェックにより、薬剤性肝機能障害を解決した症例-近森リハビリテーション病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PT-INRの変化からDo処方の増量を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ