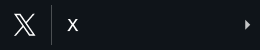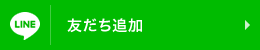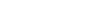薬物治療の個別最適化
HOME > 薬物治療の個別最適化
薬物治療の個別最適化
[入院患者]向精神薬多剤併用処方に介入して、過鎮静やイライラを改善した症例-JA尾道総合病院

本シリーズでは、薬物治療の個別最適化を行った事例を紹介していきます。
[入院患者]向精神薬多剤併用処方に介入して、過鎮静やイライラを改善した症例-JA尾道総合病院
今回の症例
本院(急性期病院)に、精神疾患(パーソナリティ障害)のある35歳・女性の患者さんが右下肢蜂窩織炎で入院しました。
入院時の服薬指導にて、昼間にもかかわらず患者さんはかなり眠そうで、会話をしても呂律が回っていない状態でした。また、整形外科の右下肢の治療に関して、治療方針を自分で考えることができないほどもうろうとしていました。
持参薬を見ると、向精神薬多剤併用の状態になっていました。そのため、向精神薬の翌日への持ち越し効果に伴う過鎮静や、些細なイライラにもすべて薬で対応しており、自分自身で対処する力が落ちてしまっているとアセスメントしました。
持参薬処方)
| Rp 1 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠200 mg | 1回朝1-夕1-就寝前2錠(1日4錠) |
|---|---|---|
| クロナゼパム錠1 mg | 1回1錠(1日3錠) | |
| 1日3回 朝夕食後就寝前 | ||
| Rp 2 | クロルプロマジン塩酸塩錠50 mg | 1回1錠(1日2錠) |
| 1日2回 朝夕食後 | ||
| Rp 3 | レボメプロマジンマレイン酸塩錠50 mg | 1回1錠(1日1錠) |
| フルニトラゼパム錠2 mg | 1回1錠(1日1錠) | |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10 mg | 1回1錠(1日1錠) | |
| ニトラゼパム錠10 mg | 1回1錠(1日1錠) | |
| 1日1回 就寝前 |
薬剤師が解決したプロブレム
#1 向精神薬による有害事象(過鎮静、イライラ、判断力低下)
#2 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減量による離脱症状発現のおそれ
今回の入院期間は数ヶ月と予測されており、急性期病院にしては長めであったため、向精神薬の減量を試みることが可能と考えました。そこで、週に1回診察に来られる非常勤の精神科医に対し、向精神薬の有害事象である可能性が高いことから、入院中に可能な限りの減量が望ましいことを提案しました。
また、どのように眠れないのか詳細に尋ねて、睡眠衛生指導とイライラへの対処を含めた指導を実施すべきであると考えました。精神科医もこの意見に賛同されたため、患者さんに睡眠の詳細を聴取した後に向精神薬についてのデメリットを説明、減量についての同意を取得することにしました。
減量についての計画は、下記の流れで精神科医と立案していくこととしました。
- ①患者さんとご家族に生活背景や薬に対する思い、薬剤使用歴などを聴取
- ②向精神薬減量について同意を取得するための説明
- ③精神科医へ減量計画を提案
- ④減量後の離脱症状や精神症状、睡眠の状況を確認
- ⑤問題がなければ次の減量にチャレンジ
まず、患者さんから、
・ゾルピデム(酒石酸塩)は頓服で服用していて飲んだ翌朝は起きられない
・眠れないので薬は減らしたくないが、イライラが減るなら減量してもいいかもしれない
とうかがい、ご家族(両親)からの
・薬は減らせるものなら減らしてほしい
という意向も確認できました。
そこで、患者さん及びご家族に、イライラは薬のために出ている可能性があり、減量に成功するとイライラが減ることが多いことを説明し、減量について同意を得ました。
精神科医には下記の減量計画を提案・採択され、減量に伴う不眠への対応として、睡眠薬(オレキシン受容体拮抗薬スボレキサント20 mg)が処方追加されました。
減量計画)
〈抗精神病薬〉
患者さんには、ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減量による離脱症状(不眠、イライラ、ソワソワ)を事前に説明しました。また、看護師にも同様の説明を行いました。
睡眠環境に関する思いこみがないかも患者さんに確認しながら、睡眠衛生指導を行いました。
退院時処方)(入院から7ヶ月後) ※青字は薬剤師の処方提案による変更箇所
| Rp 1 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠200 mg | 1回朝1-夕1-就寝前2錠(1日4錠) |
|---|---|---|
| 1日3回 朝夕食後就寝前 | ||
| Rp 2 | クロナゼパム錠1 mg | 1回1錠(1日1錠) |
| 1日1回 夕食後 | ||
| Rp 3 | クロルプロマジン塩酸塩錠50 mg | 1回1錠(1日2錠) |
| 1日2回 朝夕食後 | ||
| Rp 4 | レボメプロマジンマレイン酸塩錠50 mg | 1回1錠(1日1錠) |
| スボレキサント錠20 mg | 1回1錠(1日1錠) | |
| 1日1回 就寝前 |
退院時に患者さんからは、「まさか自分が薬を減らすことができると思っていませんでした。両親に感謝しつつ、自分で生活が自立できるようがんばります。」、ご家族(両親)からは「本人がハキハキと喋るようになった。ありがとうございます。」とうかがいました。
このようにして、入院時に過鎮静による眠気、イライラ、判断力低下等を認めたため、向精神薬の減量にチャレンジし、減量に伴う離脱症状や不眠の確認を行いながら減量に成功しました。
今回の薬歴
#1 向精神薬による有害事象(過鎮静、イライラ、判断力低下)
- S 「ゾルピデムは頓服で服用していて飲んだ翌朝は起きられません。今の薬がないと眠れないから、とにかく薬は減らしたくないです。でも薬を増やしても睡眠は変わらない。今もイライラしているし、どうしたらいいかわからないです。イライラが減るなら減量した方がいいのかな。」
両親「薬が多いことはわかっていたが、どうしても本人が飲みたいというので仕方なくこのままになっていた。減らせるものなら減らしてほしい。」 - O 向精神薬多剤併用。
- A 向精神薬による有害事象(過鎮静、イライラ、判断力低下)が顕著なため減量が必要。
- P 患者さん及びご家族に以下の説明をし、減量の同意を得た。「処方されている薬は、限界量以上の量が出ています。これ以上の薬の追加はできません。またイライラは薬のために出ている可能性があります。またそのために昼間も眠く、自分で考えることができなくなっている可能性があります。薬を少しずつ減らしながら、依存の少ない薬に替える方法があります。今の薬が抜ける時の離脱症状で、イライラやソワソワがあります。減量に成功された人は、イライラが減ることが多いですよ。」
患者さん及びご家族より減量の同意を得られたため、医師に提案した減量計画に沿って減量開始。
#2 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減量による離脱症状発現のおそれ
- S 患者及びご家族は減量に同意している。
- O ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減量・中止予定。
- A 起こり得る離脱症状:不眠、イライラ、ソワソワ。患者の睡眠環境に関する思い込みについても確認が必要。
- P 患者さん及び看護師に起こり得る離脱症状を説明。イライラ時はスタッフからなるべく声かけをする。患者さんに睡眠衛生指導を実施。
実務実習生の疑問に答える
Q1 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の有害事象にはどのようなものがありますか?
ベンゾジアゼピン受容体作動薬は即効性があり効果を実感しやすい反面、長期服用するにつれ「これがないと眠れない」といった依存が形成されていき、減量・中止により今まで以上の不安や不眠、ソワソワした感じ(焦燥感)などの離脱症状が発現しやすくなります。また前向性健忘や筋弛緩作用による転倒や、脱抑制といった逆に興奮や奇異な反応が出るなどの有害事象も認められています。PMDAからは、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について」1)といった注意喚起が発出されています。
Q2 睡眠衛生指導とは何を指導することですか?
誤った生活習慣のために不眠を呈している場合は、薬物治療に頼らなくても、生活習慣を変えることで不眠が改善するケースがほとんどです。眠れないと訴える人に対してすぐに薬物治療を開始するのではなく、まず睡眠に関する生活習慣について患者さんやご家族と一緒に話し合ってみましょう。例えば、アルコールをどのくらい飲んでいるか、昼寝をどのくらいしているか、朝起きる時間を一定にしているかなど、本人は間違っていると思っていないことでも、睡眠に悪影響を与える生活習慣がたくさんあると思います。
JA広島厚生連 尾道総合病院(広島県尾道市)・薬剤部。地域救命救急センター、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センター等の役割を担っている急性期総合病院で、地域内の病院・薬局等との連携に力を入れている。尾道市は元々連携に関しては実績のある地域だが、特に急性期病院からの治療経過等の情報共有ができるよう努めている。
病院紹介はこちら
URL:https://onomichi-gh.jp/
「薬物治療の個別最適化」の学修に役立つ新たなコンテンツを検討しています。
本症例への感想など、ぜひご意見をお聞かせください。
薬物治療の個別最適化

-
[入院患者]PBPMを活用して、せん妄・転倒リスクに応じた睡眠薬調整を行った症例-沼隈病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PBPMを活用して、通院でがん治療をしている患者の有害事象を解決した症例-小山記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]味を考慮した吸入剤変更提案により、高齢者の過量服薬を回避した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]暴力等が見られるレスパイト入院患者の薬物療法を多職種協働で個別最適化した症例-長野県立信州医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]入院時における初回面談と多職種連携により、ポリファーマシーや銅欠乏の疑いを解決した症例-新潟市民病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]向精神薬多剤併用処方に介入して、過鎮静やイライラを改善した症例-JA尾道総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]乳がん患者のレジメン選択支援を行い、治療が決定、身体的苦痛を解消した症例-獨協医科大学埼玉医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]高齢者の降圧薬併用による生命予後低下と副作用発現の可能性から減薬を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]認知症患者の周辺症状の増強から副作用を疑った症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]人生の最終段階にあるがん患者への疼痛コントロールでACPを実践した症例-西岡病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬剤師間連携により、潜在性甲状腺機能低下症の疑いや口腔内副作用を解決した症例-長崎病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]糖尿病患者の体調の変化から、服薬調整を指導した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]画像で心肥大等を確認し、利尿剤投与に伴う低カリウム血症を解決した症例-川口工業総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]外科的治療と歩行訓練や臥床時の圧迫やずれにより難治化した踵部褥瘡を改善した症例-小林記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]目の縁のただれから、化学療法の副作用を発見した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬物相互作用のチェックにより、薬剤性肝機能障害を解決した症例-近森リハビリテーション病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PT-INRの変化からDo処方の増量を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ