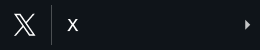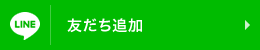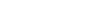薬物治療の個別最適化
HOME > 薬物治療の個別最適化
薬物治療の個別最適化
[在宅患者]認知症患者の周辺症状の増強から副作用を疑った症例

本シリーズでは、薬物治療の個別最適化を行った事例を紹介していきます。
[在宅患者]認知症患者の周辺症状の増強から副作用を疑った症例
今回の症例
いつも在宅業務として訪問している78歳・男性の患者さん(要介護2)について、同居している義理の娘さんから相談がありました。「先日、デイサービス先で大声を出したり、人を叩いたりすることがあったとのことで、この先、施設の利用を断られるのではないかと心配しています。」
処 方)
| Rp 1 | ドネペジル塩酸塩10 mg錠*1 | 1回1錠(1日1錠) |
|---|---|---|
| 1日1回 朝食後 14日分 | ||
| Rp 2 | 抑肝散エキス顆粒 | 1回2.5 g(1日7.5 g) |
| 1日3回 毎食前 14日分 | ||
| Rp 3 | リスペリドン1 mg錠*2 | 1回1錠(1日1錠) |
| 1日1回 夕食後 14日分 |
(*1:商品名アリセプト。*2:商品名リスパダール)
過去の薬歴を確認すると、2年前にアルツハイマー型認知症(AD)と診断されて、ドネペジル塩酸塩錠が開始されていました。前々月には、自分がどこにいるのかわからない、会話が成立しない、やる気がないなどという状態となり、高度ADと診断されて、「Rp 1 ドネペジル塩酸塩」がこれまでの5 mg錠から、10 mg錠に増量となりました。
デイサービスには1年前から週3回通っており、利用者とともに楽しく体操をしたり、歌を歌ったりしていました。しかしながら、1ヶ月ぐらい前から、ささいなことで怒ったり、声を荒げることが増え、先日、人を叩くという事件も起きてしまったそうです。
この周辺症状(BPSD:behavioral and psychological symptoms of dementia)に対応するために、「Rp 2 抑肝散エキス顆粒」と「Rp 3 リスペリドン錠」が追加となったと推測されました。
薬剤師が解決したプロブレム
# 興奮・易怒性症状:ドネペジル塩酸塩の増量による副作用の疑い
薬剤師は、本処方のお薬を届けた10日後に患者宅にフォローアップの電話をして、義理の娘さんに聞き取りをしましたが、まだ改善は見られないようでした。
そこで薬剤師は、ドネペジル塩酸塩の増量による興奮・易怒性の発現を疑い、医師にドネペジル塩酸塩の減量または中止を提案するトレーシングレポートを提出しました。それを受けて、次回処方では、ドネペジル塩酸塩は中止、抑肝散エキス顆粒とリスペリドンはそのまま投与となりました。
変更後処方)
| Rp 1 | 抑肝散エキス顆粒 | 1回2.5 g(1日7.5 g) |
|---|---|---|
| 1日3回 毎食前 14日分 | ||
| Rp 2 | リスペリドン1 mg錠*1 | 1回1錠(1日1錠) |
| 1日1回 夕食後 14日分 |
(*1:商品名リスパダール)
患者さんは処方変更の8日後には落ち着きを取り戻して、その後、抑肝散エキス顆粒は段階的に減量・中止となりました。最近では、再開された「ドネペジル塩酸塩5 mg/日」と、「不穏な場合にはリスペリドン0.5 mg錠の頓服服用」という処方で落ち着いています。
今回の薬歴
# 認知症周辺症状への追加処方に対する効果・副作用モニタリング
- S:怒りっぽくなった。今後が心配(家族)
- O:抑肝散、リスペリドンが処方追加
前々月に、ドネペジル塩酸塩5 mg/日→10 mg/日に増量 - A:認知症の中核症状の進行に対しドネペジルが増量されていたが、周辺症状の悪化に伴い抑肝散、リスペリドンも追加と推測
- P:追加薬剤について家族に説明。後日、電話フォローアップで効果・副作用を確認する
(処方追加から10日後、電話フォローアップ)
# 興奮・易怒性症状:ドネペジル塩酸塩の増量による副作用の疑い
- S:抑肝散、リスペリドンが追加されても、改善が見られない(家族)
- O:前々月にドネペジル塩酸塩増量。1ヶ月前から怒りっぽくなり、抑肝散、リスペリドンが処方追加
- A:処方追加で症状改善見られず。周辺症状の悪化はドネペジル塩酸塩増量タイミングと合致。ドネペジル塩酸塩による副作用の可能性あり
- P:トレーシングレポートにて、ドネペジル塩酸塩の減量または中止を処方提案
実務実習生の疑問に答える
Q1 ドネペジル塩酸塩による副作用と考えたのはなぜ?
アルツハイマー型認知症(AD)のBPSD(周辺症状)には、易怒性や興奮などの陽性症状や無欲などの陰性症状があり、本症の進行による可能性も考えられます。本症例の場合には、ドネペジル塩酸塩の増量のタイミングと合致していたので副作用が疑われました。本剤の増量の際の副作用としては、吐き気や食欲不振、軟便などコリン作動性症状、易怒性、興奮などがあげられます。
Q2 別の選択肢はなかった?
高度ADに適応をもつ薬剤は、ドネペジル塩酸塩とメマンチン塩酸塩のみです。メマンチン塩酸塩は、精神を落ち着かせる効果をもつので、ドネペジル塩酸塩を減量しつつ、メマンチン塩酸塩を併用する方法も考えられます。しかし、易怒性の原因を確認するため、あるいはポリファーマシーを回避するためにも被疑薬の減量または中止が妥当と考えました。
また、認知症の進行を完全に止める方法や、根本的な治療方法は見つかっておらず、進行を緩やかにし、生活の質を高めることが目的となっています。認知症の治療には薬物療法以外にもリハビリテーションや運動療法などサポートを受けつつ行う治療もあります。
Q3 デイサービスとは何ですか?
デイサービス(通所介護)とは、食事や排泄、入浴などの日常生活支援を受けながら交流やレクリエーションを楽しむところで、通所介護の本人の認知機能を落とさない・廃用を進めないといったポジティブな効果に加えて、家族の介護負担の軽減につながります。この患者さんの場合には、週に3回の利用で、朝8時半に車でお迎え、10時から入浴、レクリエーション、12時半から昼食、13時半から体操・趣味の時間、15時半からおやつ、16時半に自宅にお送りというスケジュールになっています。
デイサービス利用の条件としては、要介護の認定を受けた方、継続的な医療行為は不要な方などがあげられます。費用面では、介護保険が適用されるため、1〜3割の負担でサービスを利用できますが、食費やおむつ代、その他日常生活費は、実費で支払います。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140619.pdf
●執筆協力
つなぐ薬局柏・学術研修室担当 鈴木邦彦(地域薬学ケア専門薬剤師、簡易懸濁法認定薬剤師)
富士見台調剤薬局・専務取締役、帝京大学薬学部薬学教育推進センター・教授、薬剤師・薬学博士(薬理学)・臨床検査技師・医薬品情報専門薬剤師。
「薬物治療の個別最適化」の学修に役立つ新たなコンテンツを検討しています。
本症例への感想など、ぜひご意見をお聞かせください。
薬物治療の個別最適化

-
[入院患者]高齢者総合機能評価(CGA)を用いて、薬剤起因性老年症候群を把握しポリファーマシーを解決した症例-三豊総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]PBPMを活用して、せん妄・転倒リスクに応じた睡眠薬調整を行った症例-沼隈病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PBPMを活用して、通院でがん治療をしている患者の有害事象を解決した症例-小山記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]味を考慮した吸入剤変更提案により、高齢者の過量服薬を回避した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]暴力等が見られるレスパイト入院患者の薬物療法を多職種協働で個別最適化した症例-長野県立信州医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]入院時における初回面談と多職種連携により、ポリファーマシーや銅欠乏の疑いを解決した症例-新潟市民病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]向精神薬多剤併用処方に介入して、過鎮静やイライラを改善した症例-JA尾道総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]乳がん患者のレジメン選択支援を行い、治療が決定、身体的苦痛を解消した症例-獨協医科大学埼玉医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]高齢者の降圧薬併用による生命予後低下と副作用発現の可能性から減薬を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]認知症患者の周辺症状の増強から副作用を疑った症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]人生の最終段階にあるがん患者への疼痛コントロールでACPを実践した症例-西岡病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬剤師間連携により、潜在性甲状腺機能低下症の疑いや口腔内副作用を解決した症例-長崎病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]糖尿病患者の体調の変化から、服薬調整を指導した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]画像で心肥大等を確認し、利尿剤投与に伴う低カリウム血症を解決した症例-川口工業総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]外科的治療と歩行訓練や臥床時の圧迫やずれにより難治化した踵部褥瘡を改善した症例-小林記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]目の縁のただれから、化学療法の副作用を発見した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬物相互作用のチェックにより、薬剤性肝機能障害を解決した症例-近森リハビリテーション病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PT-INRの変化からDo処方の増量を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ