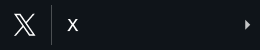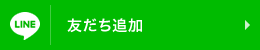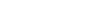薬物治療の個別最適化
HOME > 薬物治療の個別最適化
薬物治療の個別最適化
[入院患者]薬物相互作用のチェックにより、薬剤性肝機能障害を解決した症例-近森リハビリテーション病院

本シリーズでは、薬物治療の個別最適化を行った事例を紹介していきます。
[入院患者]薬物相互作用のチェックにより、薬剤性肝機能障害を解決した症例-近森リハビリテーション病院
今回の症例
階段より転落し受傷、急性期病院で脊髄損傷の診断で手術を受けた82歳・男性の患者さんが、四肢麻痺の後遺症のリハビリ目的で当院へ転院しました。合併症として全身の筋緊張と両上肢のしびれがあり、薬物治療の調整中に、医師より血液検査で著明な肝機能障害と日中の強い眠気があると、薬剤の関与について薬剤師へ相談がありました。
処 方)
| Rp 1 | プレガバリン錠75 mg | 1回1錠(1日2錠) |
|---|---|---|
| 1日2回 朝夕食後 | ||
| Rp 2 | チザニジン塩酸塩錠1 mg | 1回2錠(1日6錠) |
| 1日3回 毎食後 | ||
| Rp 3 | スボレキサント錠15 mg | 1回1錠(1日1錠) |
| ラメルテオン錠8 mg | 1回1錠(1日1錠) | |
| 1日1回 寝る前 | ||
| Rp 4 | デュロキセチンカプセル20 mg | 1回1C(1日1C) |
| 1日1回 朝食後 |
※2日前よりデュロキセチン開始。
※その他は3ヶ月以上前より服用している。
検査値)AST 457 IU/L、ALT 689 IU/L (1ヶ月前は基準値内)
超音波検査)腹部エコーでは器質的異常なし
薬剤師が解決したプロブレム
# 薬剤性肝機能障害の被疑薬の特定
今回の症例は、腹部エコーで器質的異常がなく、次の①~③の薬剤性肝機能障害に対応する考え方、
- ①薬剤性肝機能障害は入院患者では比較的起こりやすい副作用で、機序にはアレルギー性と中毒性がある
- ②アレルギー性肝機能障害は通常、新規薬剤開始後1~6週間で起こる
- ③中毒性肝機能障害は過量服用や薬物相互作用により起こり得る。処方量の問題や過量服用歴がないのであれば、薬物相互作用を確認し被疑薬を特定する
をふまえると、デュロキセチン単剤やその他の服用薬によるアレルギー性肝機能障害の可能性は低く、薬物相互作用により薬物血中濃度が上昇し副作用が生じている可能性が疑われました。チザニジン塩酸塩、ラメルテオン、デュロキセチンの3剤はCYP1A2により代謝されるため、CYP1A2による代謝が競合阻害されて血中濃度が上昇していると考え、この3剤の減量・中止を提案しました。
減量・中止後は、日中傾眠と口渇症状、肝逸脱酵素上昇も改善し、中止に伴う悪影響もなく経過しました。
今回の薬歴
# 薬剤性肝機能障害の被疑薬の特定
- S 「夜は眠れましたが、昼間も眠たくて仕方がないです……。口がとても渇きます。」
- O 検査値)AST 457 IU/L、ALT 689 IU/L (1ヶ月前は基準値内)
超音波検査)腹部エコーでは器質的異常なし - A 薬物相互作用による薬剤性中毒性肝機能障害疑い
薬物相互作用確認→チザニジン塩酸塩、ラメルテオン、デュロキセチンの3剤がCYP1A2で代謝される薬剤。この3剤による競合阻害により血中濃度が上昇し副作用をきたした可能性が高い。上記3剤は過量投与により傾眠の報告あり。この3剤の薬剤の減量・中止が必要と考える。口渇症も血中濃度上昇に伴う副作用を疑う - P デュロキセチン、ラメルテオンの中止、チザニジン塩酸塩は1回1錠へ減量し経過問題なければ中止を医師へ提案
症状変化と次回血液検査の確認
近森リハビリテーション病院(高知県高知市)・薬剤部。リハ薬剤(薬剤による生活機能低下を考慮したリハビリ)を実践中の病院であり、薬剤部は“臨床に強い薬剤部”を目指し、薬剤師1人ひとりの臨床能力の底上げに力を入れている。
薬剤部紹介動画はこちら
https://www.chikamori.com/group/recruit/pharmacist/movie/
当記事は薬ゼミの薬学生向けフリーマガジン「YAKUZEMI PLUS」No.62(2023 SUMMER & AUTUMN)P.31へ掲載したものです。
「YAKUZEMI PLUS」は、どなたでもご覧いただける「デジタルブック」を無料公開中です。
薬物治療の個別最適化

-
[入院患者]高齢者総合機能評価(CGA)を用いて、薬剤起因性老年症候群を把握しポリファーマシーを解決した症例-三豊総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]PBPMを活用して、せん妄・転倒リスクに応じた睡眠薬調整を行った症例-沼隈病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PBPMを活用して、通院でがん治療をしている患者の有害事象を解決した症例-小山記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]味を考慮した吸入剤変更提案により、高齢者の過量服薬を回避した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]暴力等が見られるレスパイト入院患者の薬物療法を多職種協働で個別最適化した症例-長野県立信州医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]入院時における初回面談と多職種連携により、ポリファーマシーや銅欠乏の疑いを解決した症例-新潟市民病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]向精神薬多剤併用処方に介入して、過鎮静やイライラを改善した症例-JA尾道総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]乳がん患者のレジメン選択支援を行い、治療が決定、身体的苦痛を解消した症例-獨協医科大学埼玉医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]高齢者の降圧薬併用による生命予後低下と副作用発現の可能性から減薬を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]認知症患者の周辺症状の増強から副作用を疑った症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]人生の最終段階にあるがん患者への疼痛コントロールでACPを実践した症例-西岡病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬剤師間連携により、潜在性甲状腺機能低下症の疑いや口腔内副作用を解決した症例-長崎病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]糖尿病患者の体調の変化から、服薬調整を指導した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]画像で心肥大等を確認し、利尿剤投与に伴う低カリウム血症を解決した症例-川口工業総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]外科的治療と歩行訓練や臥床時の圧迫やずれにより難治化した踵部褥瘡を改善した症例-小林記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]目の縁のただれから、化学療法の副作用を発見した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬物相互作用のチェックにより、薬剤性肝機能障害を解決した症例-近森リハビリテーション病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PT-INRの変化からDo処方の増量を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ