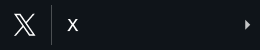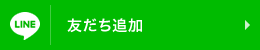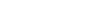薬物治療の個別最適化
HOME > 薬物治療の個別最適化
薬物治療の個別最適化
[外来患者]PT-INRの変化からDo処方の増量を提案した症例

本シリーズでは、薬物治療の個別最適化を行った事例を紹介していきます。
[外来患者]PT-INRの変化からDo処方の増量を提案した症例
今回の症例
非弁膜症性心房細動で継続受診中の72歳・女性の患者さんが来局しました。患者さんから「薬は毎日飲み忘れもなく飲んでいます。医師からは薬は同じといわれました。他に飲んでいる薬はいつもと同じです。」とお聞きしました。
処 方)ワルファリンカリウム錠1 mg 1回1錠(1日1錠)
1日1回 夕食後 28日分
検査値)PT-INR 1.45 ※臨床検査値は処方箋に記載あり
薬歴を確認し、4週間前とDo処方で、4週間前のPT-INRは2.06とわかりました。
薬剤師が解決したプロブレム
# PT-INR低下から推測したワルファリンの効果不十分
Do処方ですので、患者さんからお聞きした情報だけでは、このまま薬をお渡ししてしまいがちな症例です。処方箋に記載のあったPT-INRを薬歴に記載し継続して変動を確認していたからこそ、PT-INRの目標値からの逸脱に気づき処方提案をしたことで、個別最適化につながりました。
まず、患者さんからの聞き取りにより、PT-INRの低下は、飲み忘れや併用薬との薬物間相互作用によるものではないようです。2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドラインによると、非弁膜症性心房細動のPT-INRの至適範囲は1.6~2.6のため、4週間前と同じ用量のままでは至適範囲に達しないと推測できます。そこで、ワルファリンの増量が必要かもしれないと考え、投与量確認のため医師に疑義照会し、1日1.5 mgに増量となりました。
患者さんには、OTC医薬品や、飲み忘れ、健康食品、ビタミンKを多く含む食品の摂取に気をつけるよう、再度、説明しました。
なお、4週間後の来局時には、PT-INRは2.08と元に戻っていることが確認できました。
今回の薬歴
# PT-INR低下から推測したワルファリンの効果不十分
- S 「薬は毎日飲み忘れもなく飲んでいます。医師からは薬は同じと言われました。他に飲んでいる薬はいつもと同じです。」
- O Do処方。PT-INR 2.06→1.45↓
- A PT-INRが目標値から逸脱
- P ワルファリンの増量について疑義照会
- O2 ワルファリン1→1.5 mg↑
- P2 増量の理由を説明。アドヒアランス再確認。PT-INR変動要因と生活上の注意を説明
- Pnext 次回、PT-INRを確認
実務実習生の疑問に答える
Q1 DOACでなくワルファリンが投与されたのはなぜ?
心房細動の患者さんに対しては心原性脳塞栓症予防のために、抗凝固療法が行われます。抗凝固療法の医薬品としては現在DOAC(直接経口抗凝固薬)が主流となり、従来ほどワルファリンは使われなくなりました。ただ、腎障害などでDOACが使えない人や、DOAC発売前からずっとワルファリンで安定している人には、ワルファリンが使われています。
また、価格の面(DOACはジェネリック医薬品未発売のため高薬価)からワルファリンが選択されることもあります。今回の患者さんは、72歳で自己負担は2割でした。
なお、DOACの適応は「非弁膜症性」に限られているので、僧帽弁狭窄症や機械弁置換術後の患者さんの心原性脳塞栓症予防にはワルファリンが使われます。
Q2 PT-INRの目標値は疾患によって違うの?
ワルファリンの強度指標として、PT-INRが用いられますが、日本循環器学会他の2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドラインでは、非弁膜症性心房細動は1.6~2.6で管理、目標値が2.0となっています。二次予防や高リスクの70歳未満では2.0~3.0を考慮するとされています。
一方、僧帽弁狭窄症や機械弁置換術後では2.0~3.0で管理と、非弁膜症性心房細動の患者さんより高めの設定になっています。
Q3 患者さんのPT-INRが変化したのはなぜ?
今回の患者さんからの聞き取りではPT-INR低下の原因は残念ながらわかりませんでした。PT-INR低下の要因としては、①薬物-薬物相互作用(飲食物を含めて)、②アドヒアランスの低下、③その他の要因が考えられます。
①についてはお薬手帳に記載されていない部分も聞き取る必要があります。健康食品やビタミンK含有食品の影響も考えられます。②が原因であれば、今回の増量によって出血の危険性が高まることになるので、患者さんに再確認する必要があります。③は血漿アルブミンの変動、腎機能/肝機能の変化などが考えられます。
富士見台調剤薬局・専務取締役、帝京大学薬学部薬学教育推進センター・教授、薬剤師・薬学博士(薬理学)・臨床検査技師・医薬品情報専門薬剤師。
当記事は薬ゼミの薬学生向けフリーマガジン「YAKUZEMI PLUS」No.60(2023 WINTER)P.45へ掲載したものです。
「YAKUZEMI PLUS」は、どなたでもご覧いただける「デジタルブック」を無料公開中です。
薬物治療の個別最適化

-
[入院患者]PBPMを活用して、せん妄・転倒リスクに応じた睡眠薬調整を行った症例-沼隈病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PBPMを活用して、通院でがん治療をしている患者の有害事象を解決した症例-小山記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]味を考慮した吸入剤変更提案により、高齢者の過量服薬を回避した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]暴力等が見られるレスパイト入院患者の薬物療法を多職種協働で個別最適化した症例-長野県立信州医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]入院時における初回面談と多職種連携により、ポリファーマシーや銅欠乏の疑いを解決した症例-新潟市民病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]向精神薬多剤併用処方に介入して、過鎮静やイライラを改善した症例-JA尾道総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]乳がん患者のレジメン選択支援を行い、治療が決定、身体的苦痛を解消した症例-獨協医科大学埼玉医療センター
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]高齢者の降圧薬併用による生命予後低下と副作用発現の可能性から減薬を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[在宅患者]認知症患者の周辺症状の増強から副作用を疑った症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]人生の最終段階にあるがん患者への疼痛コントロールでACPを実践した症例-西岡病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬剤師間連携により、潜在性甲状腺機能低下症の疑いや口腔内副作用を解決した症例-長崎病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]糖尿病患者の体調の変化から、服薬調整を指導した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]画像で心肥大等を確認し、利尿剤投与に伴う低カリウム血症を解決した症例-川口工業総合病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]外科的治療と歩行訓練や臥床時の圧迫やずれにより難治化した踵部褥瘡を改善した症例-小林記念病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]目の縁のただれから、化学療法の副作用を発見した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[入院患者]薬物相互作用のチェックにより、薬剤性肝機能障害を解決した症例-近森リハビリテーション病院
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ

-
[外来患者]PT-INRの変化からDo処方の増量を提案した症例
薬物治療の個別最適化を掲載しました。
- 学ぶ